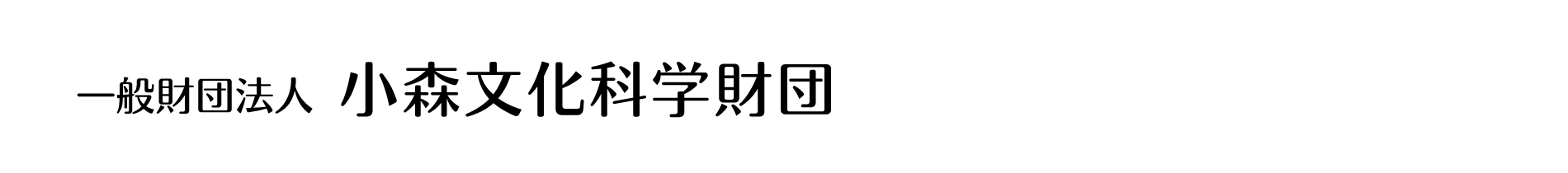助成先事業実績
2024年度 助成先の事業実績
1.香取市立佐原中学校(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 佐原囃子用楽器整備事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 本校は佐原の伝統文化を継承し、郷土芸能部の活動を続けている。2月の新年のつどいでは、助成を受けた楽器を初めて演奏する予定である。 |
| 実施効果 | これまでは簡易的なプラスチック製の楽器を使用していたが、助成により本皮の楽器で稽古できるようになった。音を出すのに苦労しつつも良い学びとなっており、指導者の教えのもと丁寧に扱うことで演奏も向上してきている。今後はさらなる技術向上を目指している。 |
| 今後の目標など | 郷土芸能部は「佐原の大祭」に欠かせない佐原囃子の伝統を次代に引き継ぐことを目指し、活動を継続している。各種行事に参加して演奏を披露することで、佐原の伝統芸能を広めるとともに、後継者の育成にも貢献していきたいと考えている。 |
2.香取市立佐原小学校(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 佐原囃子用既存楽器の最適化事業(演奏に使用する楽器の最適化) |
|---|---|
| 事業内容 | 郷土芸能部の楽器整備 |
| 実施効果 | これまでの助成金により、佐原囃子の練習や発表に必要な楽器・備品を整えることができた。本年度は10月8日の音楽発表会に出演し、助成を受けて仕上げた小鼓の白皮により、今後の本格的な演奏を子どもたちも楽しみにしている。整備された楽器への感謝の気持ちを育みつつ、道具の扱いや音の質への意識向上を目指して、今後も指導・支援を続けていく。 |
| 今後の目標など | 楽器の整備を通じて佐原囃子への意欲と演奏技術の向上を図るとともに、道具を大切にする心や伝統が多くの人々に支えられて継承されていることに子どもたちが気付けるよう、指導・支援を行っていく。郷土芸能部の活動をさらに推進し、地域の伝統文化の継承と子どもたちの郷土愛や豊かな心の育成につなげていく。 |
3.千葉県立佐原高等学校(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 佐原囃子伝承事業(アメリカウィスコンシン州での佐原囃子披露の為の楽器整備、準備費用) |
|---|---|
| 事業内容 | 2024年10月26日~11月3日に実施されるウィスコンシン州千葉県友好使節団として、佐原高校郷土芸能部の2年生6名を派遣を実施 |
| 実施効果 | ウィスコンシン州では、WYSOでのホストファミリー向け演奏をはじめ、イーストハイスクール、ストートンハイスクール、州庁舎、オークウッドヴィレッジ老人ホームの計5か所で公演を行い、いずれも大盛況だった。佐原の祭りの踊り体験や佐原囃子の楽器体験も実施し、現地の高校生や一般の人々との文化交流を盛り上げることができた。 |
| 今後の目標など | アメリカ・ウィスコンシン州での文化体験・交流を通じて両国の文化の素晴らしさを改めて実感し、その経験を活かして、佐原囃子の魅力をより多くの人に伝えられるよう部員一同練習に励み、地域への発信に努めていきたい。また、来年度以降も新入部員の勧誘を行い、創部58年目を迎える佐原高校郷土芸能部の伝統を今後も継承していきたい。 |
4.牧野下座連(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 下座演奏用楽器修繕事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 佐原囃子の下座演奏で使用する大太鼓の両面皮張替、及び胴内の修理 |
| 実施効果 | 牧野下座連が使用する大太鼓は、明治時代に東京浅草の「鉄石」から購入されたと推測され、昭和以降に少なくとも3回皮の張替を行ってきた。長年の使用による劣化で音が変わってしまっていたが、今回両面皮の張替と胴内のひび割れ修理を行ったことで、戦前に“佐原囃子の名器”と称された「牧野の大太鼓」の音色の復活が期待されている。 |
| 今後の目標など | 張り替えた厚皮の大太鼓を長年叩き込みながら音色を熟成させることで、日本三大囃子の一つである佐原囃子の演奏技術をさらに高め、牧野下座連の発展と次世代への継承を図る。 |
5.下仲町区(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 地域伝統文化の修繕・保存事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 老朽化した山車蔵を災害に強い蔵に建て替え、ユネスコ無形文化遺産の山車を保護・継承し、地域文化を後世に伝える。 |
| 実施効果 | 新しい山車蔵の完成により、災害に強くなり、地域の伝統文化の保存・活用がさらに進むと考えられます。 |
| 今後の目標など | 下仲町区は町内が小さく文化財の維持が困難ですが、今後も飾り物の修繕などを行い、伝統文化の継承と山車の整備保護に努めていきます。 |
6.宮川伝統芸能保存会(岐阜県飛騨市)
| 助成事業名 | 地域伝統文化の修繕・保存事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 本事業は、後継者不足により存続が危ぶまれている地元芸能を継承する有志団体による取り組みであり、助成金により老朽化した備品(唐傘、衣装、太鼓バチ等)の新調が実現し、公演への支障が改善された。また、これまで無償で協力を得ていた着付け等についても、今回から適切な対応が可能となった。 |
| 実施効果 | 当地の珍しい民踊「みやがわ古大尽」は、各種イベントで好評を得ており、今回の助成金により修理を重ねてきた衣装や用具を新調することができた。さらに、「越中おわら」の踊りを中学生にも指導し、文化祭で披露することができ、地域住民からも高い評価を得た。 |
| 今後の目標など | コロナ禍以降のイベント縮小や会員の高齢化により運営が厳しくなっているが、今回の用具新調を機に、郷土芸能の継承と各地での公演により積極的に取り組んでいきたいと考えている。 |
7.かとり町並みあーと倶楽部(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 古典芸能(長唄・日舞•お囃子)の演奏会の実施 |
|---|---|
| 事業内容 | 令和7年3月15日(会場:寿茂登、18時30分開演)および16日(会場:いなえ、13時30分開演)に長唄鑑賞会を開催した。国内で活躍する若手演奏家による演奏と舞踊が披露され、「佐原音頭」「佐原小唄」「水郷小唄」など、佐原の大祭で演奏機会が減少している演目を中心に構成された。また、古典芸能の普及を目的に、鼓や三味線の独演も取り入れた演奏会とした。 |
| 実施効果 |
3月15日の「寿茂登」での演奏会には25名の来場者を迎え、初めて長唄を間近で聴く方も多く、大変感動されていた。長唄という古典芸能を身近に感じていただけた機会となった。 また、3月16日の「いなえ」では小規模な会場ながら日舞の上演も行われ、観客の目の前で披露された舞踊は非常に魅力的に受け止められた。外国人観光客も来場し、日本文化に直接触れられたことを喜んでいた。 |
| 今後の目標など | 回を重ねるごとに、佐原と古典芸能との結びつきが深まり、新たな文化が生まれ育ってきたことを実感している。今後もこの会を継続し、さらに発展させていきたい。 |
8.飛騨古川四神太鼓(岐阜県飛騨市)
| 助成事業名 | 飛騨古川四神太鼓 |
|---|---|
| 事業内容 |
飛騨古川四神太鼓 結成30周年記念公演 日時:2024年11月24日(日) 会場:飛騨市文化交流センター スピリットガーデンホール 内容:メンバー(大人・子ども)、OB、ゲストのホワイトパールによる迫力ある太鼓演奏 |
| 実施効果 | 照明も強化され、太鼓の演奏や演出がとても良いものとなり、観客の方々から高い評価をいただきました。 |
| 今後の目標など | 太鼓の演奏を通じて人とのつながりを深め、子どもたちにも伝統芸能の素晴らしさを伝承していく。 |
9.明暮れ小唄(東京都渋谷区)
| 助成事業名 | 地域文化の継承・公演事業 |
|---|---|
| 事業内容 |
実施日時:2024年10月19 日(土) 上演内容:映写した画像:葛飾北斎、歌川広重、川瀬巴水など49作品 演奏した小唄:五月雨や、浜町河岸等24作品 |
| 実施効果 | 北斎小唄の番外編では、葛飾北斎以外の浮世絵や古写真、現代アーティストによる作品を取り入れ、隅田川の橋への親近感を高める内容となった。総合演出に大和田文雄氏を迎え、伝統芸能と歴史建築が融合した充実した舞台が実現し、地域の歴史文化への郷愁を呼び起こす公演となった。また、今回から小唄の歌詞を字幕で映写し、見やすさに配慮した演出が観客から好評を得た。 |
| 今後の目標など | 北斎小唄の続編を継続上演し、舞台の充実と上演回数の増加を通じて地域での認知度を高め、小唄による「地域文化の再発見」を目指していく。すみだ北斎美術館の「イベントパートナー制度」を活用し、小規模ライブや体験講座、地域の老舗店との連携による物販なども行い、集客向上を図る。最終的には、音楽ユニット「明暮れ小唄」として、小唄の社会的認知と普及、演奏者の技術向上、小唄の伝承に寄与することを目的とし、伝統的な芸術や建築と融合した舞台芸術としての可能性も探っていく。 |
10.株式会社長崎検番(長崎県長崎市)
| 助成事業名 | 地域文化の継承・公演事業(演舞の際に使用する小道具の購入) |
|---|---|
| 事業内容 | 長崎検番では、季節に応じた演目に合わせて花笠やもみじ、あやめなどの小道具を多用しており、これまで経年劣化した小道具を自ら修繕しながら使用してきた。今回の助成金により、それらの小道具を新調することができた。 |
| 実施効果 | 新調した小道具は、料亭でのお座敷や「長崎検番 in 出島」などのイベントで活用し、長崎検番の魅力をより多くの人に発信していく予定です。 |
| 今後の目標など | これまで以上に、国内外の多くのお客様に魅力ある演舞を披露する機会を創出するとともに、長崎の古き良き伝統芸能の振興と芸妓衆の後継者育成に努めてまいります。 |
11.関西学院大学社会学部(兵庫県西宮市)
| 助成事業名 | 地域の伝統文化出版事業(「奄美学」の成果公開と普及・啓蒙のためのブックレット出版) |
|---|---|
| 事業内容 |
奄美大島で実施してきた「奄美学」の成果を、地元市民はもとより広く社会に還元するため、以下のブックレットを刊行する。 久留ひろみ・島村恭則 編『奄美学への招待:新時代の地元学』南方新社、2025年3月刊行。 |
| 実施効果 | 本書のもととなった奄美市生涯学習講座「みんなの奄美学」の受講者数は、刊行後に前年の約50名増となる100名へと倍増した。また、本書の刊行を契機として、地元および島内外の奄美学研究者による「奄美学術会議」が設立されることになり(2025年5月31日に設立総会予定)、今後の奄美学の発展が期待されている。 |
| 今後の目標など | 2025年度に本財団の助成事業として採択された「『奄美学』の担い手育成に資するフィールドワークとワークショップの実施」を着実に遂行するとともに、前述の「奄美学術会議」とも連携し、奄美学のさらなる深化に努めていく。 |
12.一般財団法人国際協力推進協会(東京都千代田区)
| 助成事業名 | APIC留学生の地方都市における伝統文化体験・人的交流(APIC留学生丹波篠山研修) |
|---|---|
| 事業内容 |
2025年3月12~14日、太平洋・カリブ地域からの上智大学留学生5名が、奨学金支援の一環として丹波篠山で国内研修を行った。 研修では、郷土料理作り(獅子汁・黒豆寿司)や陶芸体験、森林保全の現地活動見学を通じて、日本の地域文化や暮らし、歴史について深く学んだ。 また、地域住民との交流や英語解説による施設見学を通じて、日本社会への理解も深まった。 特に日本の治安や人々の親切さに感銘を受ける場面もあり、異文化理解と相互交流を促進する有意義な機会となった。 |
| 実施効果 | 本研修を通じて、丹波篠山の文化・歴史・暮らしへの理解が深まり、日本を多角的に捉える力が養われた。また、現地の人々との交流により相互理解が進み、陶芸体験や林業視察を通じて日本の伝統技術や自然との共生の知恵への敬意や学びが得られた。 |
| 今後の目標など | 本研修は、東京での留学生活では得られない貴重な経験を通じて、地方の伝統文化や人的交流に触れる機会を留学生に提供し、日本への理解と相互理解を深める有意義な取り組みであることが確認された。今後も留学生の希望を反映しながら、文化体験や交流の機会を継続的に企画・実施し、彼らが将来的に日本と母国をつなぐ存在となることを期待している。 |
13.上智大学大学院地球環境学研究科(東京都千代田区)
| 助成事業名 | 奄美大島宇検村豊年祭への学生参加活動事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 本事業は、奄美大島宇検村の伝統行事・豊年祭への参加と支援を通じて、地域住民との交流を深め、自然環境の保全と地域活性化を両立させる新たなツーリズムの可能性を提言するものである。行事後には区長らへのヒアリングやワークショップを実施し、地域資源の活用や持続可能な観光の在り方を議論。一過性でない中長期的な地域連携の基盤づくりを進めている。 |
| 実施効果 | 学生は豊年祭の運営支援と併せて文化・自然環境の調査を行い、宇検村に提言を実施。住民からは祭りの活性化や支援への感謝の声が寄せられ、学生からも伝統文化への理解が深まったとの好評があった。本事業は、地域文化の継承と若者・国際交流の促進という二重の効果を上げている。 |
| 今後の目標など | 行事後のヒアリングでは、豊年祭の継続や地域の国際的魅力発信、小中学生との交流への期待が示された。今後は豊年祭支援を継続しつつ、教育支援や自然体験など他の地域活動にも広げ、地域住民との交流を深めながら持続可能な地域づくりを目指す。 |
14.特定非営利活動法人佐原アカデミア(千葉県香取市)
| 助成事業名 | 大学と地域の拠点交流センター運営事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 日本遺産の佐原地域を拠点に、大学との連携による人材育成や地域活性化を目的とした様々な活動を実施。学生によるフィールドワークやワークショップ、国際交流、発酵をテーマにした地域イベント(発酵フォーラムや全国発酵食品サミット)を開催し、地域資源の活用と持続可能なまちづくりを推進した。 |
| 実施効果 | 大学との連携を深め、学生と地域の関係人口を育んでいくことで、市民との交流が深まり、佐原に深く携わってくれる人材が育成されることが期待できる。 |
| 今後の目標など | コロナ禍以前のように大学との連携を再活性化し、インターンシップやゼミ研修などの実践的な学びを通じて、感性を育むまちづくり教育を推進する。これにより、関係人口の育成と地域の持続可能性の向上を目指す。 |
15.江戸東京学・水都佐原調査研究会(千葉県佐倉市)
| 助成事業名 | 発酵フォーラム開催事業 |
|---|---|
| 事業内容 | 江戸時代から醸造業が発展してきた佐原地域で、香取市と法政大学が連携し、「発酵のまちづくり」を推進する一環として、2024年9月に「発酵フォーラム」を開催した。フォーラムでは、イタリアの地域づくりの概念「テリトーリオ」をテーマに、持続可能な地域発展と発酵文化の活用について議論が行われた。参加者からは好評を得て、地域関係者との交流や現地視察も実施された。 |
| 実施効果 | 発酵のまちづくりを進めるには、地域全体を見据えた視点でスローフードとしての発酵を捉えることが重要であり、そのような地域に根ざしたまちづくりの必要性が共有された。 |
| 今後の目標など | 今後も法政大学エコデザイン研究センターと連携し、佐原のまちづくりのために、歴史や伝統・文化を学び未来を考える場を提供していく。 |
16.一般社団法人コネクトプラス(岐阜県飛騨市)
| 助成事業名 | 自然探究キャンプ〜自然のつながりを時明かそう〜 |
|---|---|
| 事業内容 |
2024年10月12日〜14日に「国立乗鞍青少年交流の家」にて、小学5・6年生13名を対象とした自然探究キャンプを実施。雲や水の循環など自然のつながりについて、講義・実験・ハイキング・ワークショップなどを通じて体験的に学んだ。 本事業は、国立乗鞍青少年交流の家の提案により、株式会社Edo、一般社団法人コネクトプラスと共同で実施され、教育委員会の後援も受けた。 |
| 実施効果 | 飛騨地域の自然や気象、地理への理解を通じて、子どもたちが地域の伝統や産業に興味を持つことを目的にワークショップを実施。狙い通り、自然・伝統・生活のつながりを実感したという感想が多く、最大の成果となった。特に最終日の活動をきっかけに、参加者は冬休みに地域の伝統産業(山中和紙や飛騨の匠など)を自主的に調べ、学びを深めた。 |
| 今後の目標など | 今回は小学校高学年を対象に実施したが、今後は対象年齢を広げ、視点を変えながら飛騨の伝統・産業・自然を幅広く伝えていきたい。また、親子での学びが家庭での体験につながることも期待されるため、親子向けの企画やPTAとの連携も検討している。 |